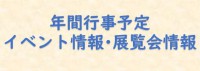火起こし体験解説
※スマートフォンだとうまく表示されないようです。適宜拡大してご覧ください。
考古博物館では、まいぎり式の方法で火起こし体験を実施しています。
道具は画像の一式を用意し、周りに何もないことを確認して行います。(数組で行う場合は互いに距離をとって行うようにしましょう。)

道具一式
1.火きり棒にヒモを巻き付け、棒の先を受け皿の小さいくぼみに合わせます。持ち手を下げ、回転をさせます。
持ち手を下げる際に力を入れ、下まで降りたら力を緩めます。ヨーヨーのように、ヒモは下におろすと伸びますが反動で自動的に棒に巻き付きます。ヒモが巻かれる勢いで持ち手は上に上がる力が働きます。(この時に無理に上にあげようとするとヒモは棒に巻き付かなくなり回転が止まってしまいます。)
この動作をひたすら繰り返します。

臼に軸棒を当てている様子 |

軸棒を回転させている様子 |
2.棒の先と受け皿には回転によって摩擦が生じます。この摩擦によって受け皿のくぼみが削れていき、木の粉が出てきます。さらに摩擦熱が木の粉に移ることで火の赤ちゃんでもある“火種”が出来上がります。
(木の粉から煙が出てくれば火種ができている合図になります。一緒にやる方に見ていてもらいましょう。摩擦熱が生じているので回転している部分からも煙が出ますが火種の煙と間違えないように気を付けてください。また、大変熱く(約600℃)なっているので触らないようにしましょう。)

木の粉が出てきている様子 |

出来上がった火種 |
3.火種は、麻ヒモをほぐして作った火口(ほくち)に優しく移し、軽く包みます。

火種を火口に移す様子 |

火種を包んでいる様子 |
4.軽く包んだ麻を竹ばさみでしっかりと掴み、腕を大きく振ります。
(竹ばさみで火種をつぶさないように、火口の中心をずらして掴みます。)

竹ばさみで掴んでいる様子 |

腕を振り空気を送り込んでいる様子 |
5.火口に空気を送りこむことによって火種が大きくなり、火がつきます。
(火がつく前は煙の量が大きくなります。しっかりと火口を見て腕を伸ばすようにしてください。また、火がついたら腕をちょっと上に向けます。びっくりして腕を下げてしまうと火は自分の体のほうに上ってきてしまいやけどの原因となってしまいます。)

火がつきました |

安全のため水の中へ |
当館では、このような要領で火起こし体験を実施しています。
考古博物館での体験はもちろんのこと、小学校やその他施設での出前講座や道具の貸出を行っております。お気軽に考古博物館までご連絡ください。