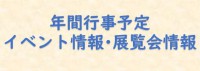常設展展示紹介③ 「縄文時代の土器2」
いろんな形の縄文土器(深鉢・浅鉢)
深鉢は縄文土器の中で、最も多い土器の形です。おもに、煮る、炊く、蒸す、蓄えるなどの目的で使われました。これに対して浅鉢は、食べ物を盛り付けるために使われました。現在の皿や鉢にあたるものです。

深鉢

浅鉢
いろんな形の縄文土器(釣手土器・有孔鍔付土器)
縄文土器には、器としての用途だけでなく実用的な製品として作られたと考えられるものも有ります。その一つが、釣手土器です。釣手土器は縄文時代中期中ごろから後半にだけ作られた極めて特殊な土器です。鉢にとっ手がついたような形をしています。内側がすすけているため、ランプとして使われたと考えられます。

釣手土器
コラムクイズ
縄文土器には釣手土器の他にも実用的な製品があります。
考古博物館に展示している下記の土器の口の部分にはほぼ等間隔で小さな穴があけられ、その下に鍔(つば)がついています。口に皮を張って太鼓としたとする説と、酒を造るための容器だったとする説(穴はガス抜きのために使った)があります。では、このような土器を何というでしょうか?

3つの中から選択してください