vol.117 日本刀は美しい?
神事によって幕開けした特別展「日本刀は美しい Japanese Swords Are Beautiful」が10月2日(水)から始まりました。特別展の担当学芸員として、特に苦労したことなどこのコラムを通して共有できたらと思います。
 |
私は約3年前にこの刀剣展の担当となりました。当初はなんの因果で刀剣の展示を任されるのかと葛藤していましたが、考えてみれば理由は単純で、私が美術系の学芸員であったからでした。学芸員資格というのは学んだ専門分野に応じて、美術系、歴史系、自然系などと分かれています。美術系の学芸員である私が刀剣を扱うということは、とりも直さず刀剣が美術品であるということなのです。しかし、当初は日本刀が美術品であるという認識がなく、展示を見ても素通りするような、むしろ避けて通っているような状況でした。日本刀の人を斬るという血なまぐさいイメージが苦手でしたから、展示準備に向けてはゼロからスタートを切ったというよりマイナスからのスタートだったのです。
それでも担当するからには良い展示を目指したい。そこでまずは、刀を観ることから始めました。東京国立博物館、刀剣博物館、静岡の佐野美術館、茨城の徳川ミュージアム、広島のふくやま美術館、岡山の備前長船博物館など、初めて意識的に日本刀を観ました。同時に、今回の刀剣展の監修をお願いした日本美術刀剣保存協会長野県南支部の会員さんの指導を受けて、実際に刀を手に取って鑑賞する機会も設けていただき、当館の所蔵刀を用いて実際に刀を手入れする練習も行いました。R6年3月には「収蔵品刀剣展」、その年の暮れには「年越し刀剣展」と実際の展示を通して実績を積みました。
日本刀について学んでいくうちに強く思ったことがあります。それは武器として以上に日本刀が日本人の生活に強く根ざしているということでした。日本刀というものを意識して生活をしてみると、普段何気なく使っている日本語に刀を語源とするものが数多くあるということに気づかされます。「切羽詰まる」「付け焼刃」「もとの鞘に収まる」など、日常会話に刀由来の言葉がどんどん出てきます。それは刀が武士だけのものではなく庶民の暮らしにしっかりと根付いていたからこそ、今でも残っているのです。また、江戸の庶民の娯楽であった歌舞伎や落語にも刀の題材を多くみることができます。さらに、日本最古の書物と言われる「古事記」の冒頭で、イザナギとイザナミが国生みを行う際に用いた道具「あめのぬぼこ」の矛とは刀のことです。日本刀は血なまぐさい殺戮の道具としてよりも人々の畏敬の対象として、生活に必要な守り刀として、日本人の生活になくてはならないものだったのです。
当初、この展示のタイトルは「国宝で知る初めての刀剣」というものでした。「日本刀は美しい」というタイトルになったのは、様々な葛藤と試行錯誤を経て自分自身が心から「日本刀は美しい」と思えるようになってからです。そしてそう言えるようになったのはやはり、日本刀の基礎的な知識を学び、鑑賞の目が養われたからだと思います。この展示ではまず、その日本刀を観る時に必要な基本的な知識をわかりやすく展示しています。それは私自身の3年間の学びを凝縮したものになっています。30年40年と学んでいる方々に比べると「付け焼刃」の知識ではありますが、日本刀を学ぶ出発点にはなるかと思っています。
会場は「日本刀を知る」「日本刀を作る」「日本刀を観る」の3章に分かれています。まず、プロローグ「守り神としての日本刀」で四柱神社からお借りした反りのない直刀を見ていただきます。これは神宮式年遷宮のために昭和28年(1953)に当代きっての名工が古式に則って作刀したものです。20年ごとにお社も神宝も調度品もすべてを同じように新しく作り変える大行事、神宮式年遷宮は約1300年前、持統天皇の時代に始まっていますので、この直刀によって奈良時代の刀の姿を見ることができます。
 |
1章、2章は白い空間で構成されています。「日本刀の特徴1」では「長さを見て種類を知る」というテーマで、太刀、打刀、脇差、短刀の4種類の刀身を縦に展示しています。長さの比較はイラストを使ってパネルにして掲示するのが一般的ですが、刀身現物を縦に展示したいという私の希望を宮入法廣刀匠が汲んでくださって、オリジナルの刀掛けを設計してくださいました。特徴2~6でローケースに横たえて展示するために使っているアクリル刀置きも、刀匠の設計でオリジナルで作っていただきました。
 |
右側ウォールケースの日本刀の特徴のコーナーでは、日本刀に反りが生まれる過程の初期の形である「毛抜形太刀」から始まり、時代を追って刀の歴史的変化をトピックスとして取り上げています。日本刀の歴史は入り口右手にある年表でも詳しく見ることができます。
 |
次のコーナー、通称「辞書部屋」では刀にまつわる日本語から日本人の生活にいかに日本刀が浸透しているかを知っていただけたらと思います。「もとの鞘に収まる」「切羽詰まる」「鍔迫り合い」「懐刀」「目貫通り」の5つを特に取り上げて、言葉の由来となった鞘や鐔、目貫を紹介しています。
 |
第2章では「刀剣を作る」というテーマで、宮入法廣刀匠のコーナーを作りました。刀匠の作刀風景の映像と刀を作る紹介パネル、そして、宮入刀匠が作刀した、国宝骨喰藤四郎の再現模造を360度どこからでも見られるように展示しています。今回の展覧会では刀掛けの設計、図録への執筆、映像への出演とたくさんのご協力をいただきました。
刀匠が鍛冶場を構えている東御市の梅野記念絵画館で、11月15日から「刀が映す東御の歴史」を開催予定です。埼玉で発掘された「稲荷山古墳出土金錯銘鉄剣」や正倉院宝物刀子の再現模造も展示されますので、ぜひそちらにも足をお運びください。
 |
さて、ここまでが前半の白い空間です。後半第3章からは「日本刀を観る」と題して黒い空間が現れます。当館アソシエイトプロデューサーのおおうちおさむがオープニングで述べたように、黒という色は「終焉」や「畏敬」を暗示させるもので、日本刀の美しさを鑑賞するにふさわしい空間になっています。刀掛けに掛ける布も黒にしましたが、この布の選定には苦労しました。本来なら白の羽二重(絹)を掛けるのですが、これを黒にすると光を受けて反射してしまい刀のよさを殺してしまいます。そこで10種類以上の布を試して、マットな黒で反射の少ない綿のギャバジンという種類を使うことにしました。
黒い空間に展示された刀25振りはすべて言わずと知れた名刀ばかりです。前半の日本刀に対する知識を持って鑑賞するとそれぞれの刀が放つ底知れない美しさが見えてくると思います。
 |
 |
「日本刀は美しい」というタイトルの大きさに気が引ける思いもありましたが、日本刀は美しいと言い切ることによって、会場全体にも美しさがもたらされたように思います。
どんなものにも畏敬の念を持って美しさを見出そうとする日本人の美的感性に日本刀を通して少しでも触れていただければ幸いです。この展示を通して、ただの鉄の塊にしか見えなかったものが究極の美術品に変化していくおもしろさを体験できるかもしれません。
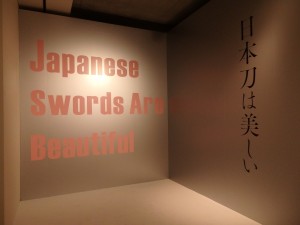 このエントランスのコーナーに立って写真を撮ると誰でも素敵に取れますのでぜひ。 |
令和7年度特別展「日本刀は美しい Japanese Swords are Beautiful」
■会期 令和7年10月2日(木)~11月16日(日)
■開館時間 9時~17時(入館は16時30分まで)
■閉室日 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)
■会場 松本市立博物館2階特別展示室
■観覧料
単独券 一般1,100円(900円)、大学生700円(600円)
常設展とのセット券 一般1,300円 (1,100円)、大学生800円 (700円)
高校生以下無料 ()内団体料金


